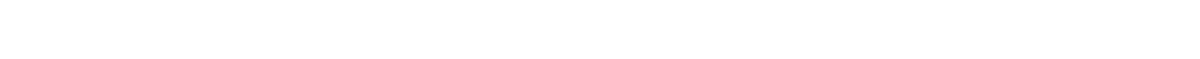MXR Dyna Compは「つぶし」と「前に出る感じ」をシンプルに作る名機。だがノブが少ないぶん、わずかな差で使い勝手が激変する。
この記事では“MXR Dyna Comp セッティング”の検索意図に直球で応え、ピックアップ別・演奏スタイル別の具体値を提示。
まずは今日から試せる実践的な初期値から始めよう。
目次
MXR Dyna Comp セッティングの初期値
Dyna Compの2ノブ(Output / Sensitivity)は、どちらも小さな動きで音が変化する。ここでは、まず「失敗しない初期値」として最も安定した位置を示す。
| 用途 | Output | Sensitivity | 解説 |
|---|---|---|---|
| クリーン基準 | 1時 | 10〜11時 | 弾きやすく、自然なつぶし。Dyna Compの定番。 |
| 歪み前ブースト | 2時 | 9〜10時 | 歪みの粒が立ち、音抜けが良くなる。 |
| 常時ON | 12時半 | 9〜10時 | 弾き心地を整える用途。ほぼ原音に近い。 |
| リード強調 | 1時半 | 12〜1時 | サステインを伸ばし、音を太くする。 |
まずはこのどれかを選び、耳で「違い」を感じながら少しずつノブを回す。Dyna Compは“回す前に考える”よりも“回して確認する”ほうが早い。
OutputとSensitivityの意味と回し方
Dyna Compのセッティングを理解するには、この2つのノブの関係を知ることが不可欠だ。見た目はシンプルだが、実際はかなり奥が深い。
Output(アウトプット)=音量+押し出し感
Outputは「コンプレッサーで小さくなった音をどれだけ持ち上げるか」を決めるノブ。つまり、最終的な音量と存在感をコントロールしている。
- Outputを上げる → 音が太く、前に出る。
- 下げる → 自然でフラットな音になる。
- クリーン時は1時前後が基準、歪み前では2時が目安。
音量を上げるときだけでなく、曲中で「もう少し抜けがほしい」と感じた時にもOutputを+15分程度動かしてみると良い。
Sensitivity(センシティビティ)=圧縮量と反応の速さ
Sensitivityは「どのくらい強く圧縮をかけるか」を決めるノブ。内部的にはスレッショルドとレシオを同時に変えている。
- Sensitivityを上げる → 小さな音まで圧縮、つぶしが強くなる。
- 下げる → ナチュラルで原音に近い。
- 10〜11時が標準。12時を超えると“コンプらしさ”が強調される。
重要なのは、この2つのノブを「片方ずつ動かさない」こと。Sensitivityで圧縮量を決めたら、Outputでその分を補う――これがMXR Dyna Comp セッティングの基本的な流れである。
ピックアップ別|MXR Dyna Comp セッティング
Dyna Compの反応はピックアップ出力に強く依存する。ここでは、シングル・ハム・P90の3タイプごとにおすすめの設定を紹介する。
シングルコイル(ストラト・テレキャスターなど)
- クリーン:Output 1時/Sensitivity 11時
- ファンク・カッティング:Output 1時半/Sensitivity 12時
出力が低めなので、少し強めにコンプレッションをかけると輪郭が整う。ファンク系ではアタックを残すためにSensitivityを上げ、Outputで押し出すのがコツ。
ハムバッカー(レスポール系)
- クリーン:Output 12時半/Sensitivity 10時
- リード:Output 2時/Sensitivity 11時
ハムバッカーは出力が強いため、Sensitivityを上げすぎると音がつぶれすぎる。少し控えめにして、Outputで厚みを補うと音抜けが良くなる。
P-90
- クリーン:Output 1時/Sensitivity 10時半
- バッキング:Output 1時半/Sensitivity 10時半
中域が太く出るP-90は、コンプレッションがかかりやすい。Sensitivityを抑えて原音の勢いを残すと、バンド内でも抜けるサウンドになる。
演奏スタイル別|用途で決めるDyna Comp設定
スタイルごとに狙いが変わる。以下の数値は、現場で即使える設定の目安だ。
カッティングを前に出す
Output 1時/Sensitivity 12時
→ 中域を引き立て、弦の粒立ちを整える。ファンク・ポップ系に最適。
カントリー/チキンピッキング
Output 1時半/Sensitivity 1時
→ アタックを強調しつつ、ピッキングの強弱を均一化。軽快な立ち上がりを作れる。
歪みの締まりを出す
Output 2時/Sensitivity 10時
→ 歪み前に置くとローが締まり、ミッドレンジの抜けが強調される。ソロでの粒立ちも良くなる。
常時ONで整える
Output 12時半/Sensitivity 9〜10時
→ 聴感上のコンプ感は少ないが、弾き心地が安定し録音にも向く。
ペダルボード内の置き場所と接続順
Dyna Compはギター直後(歪み前)に置くのが基本。
これにより、ピッキングの強弱が整理され、後段の歪みがコントロールしやすくなる。
| 組み合わせ | 推奨順序 | 効果 |
|---|---|---|
| ワウ+Dyna Comp | ワウ → Dyna Comp | ワウのレンジが安定。ノイズも少ない。 |
| フェイザー+Dyna Comp | Dyna Comp → フェイザー | モジュレーションが自然に溶ける。 |
| 歪み後段に置く場合 | 歪み → Dyna Comp | リードの音量を整えるときのみ有効。 |
電源は9Vセンターマイナス。ノイズを減らすならアイソレート電源が理想だ。
モデル別の特徴と設定傾向
Dyna Compには複数モデルがある。ここでは主要3機種の違いを整理する。
Classic(M102)
最も定番の2ノブ仕様。ヴィンテージ系の「つぶし」が特徴で、ファンクや70年代ロックに強い。
Mini Dyna Comp
小型筐体ながらAttackスイッチ搭載。
Fastではパンッと前に出る反応、Slowでは滑らかに伸びる。歪み前で使うならSlowが自然。
Deluxe Dyna Comp
Tone・Clean・Attackを追加した多機能版。
特にCleanブレンドが優秀で、原音を混ぜて自然なコンプを作れる。
ベースや高出力ギターにも対応しやすい万能機。
失敗あるあると修正フロー
音がこもる・抜けない
→ Sensitivityを-15〜-30分。DeluxeならToneを+方向へ。
つぶれすぎて弾きにくい
→ Sensitivityを下げ、Outputを+15分上げて音量を戻す。
ノイズが増える
→ Sensitivityの上げすぎが原因。歪み後段配置も避けよう。
電源共有をやめるだけでノイズが減ることも多い。
パンピング(呼吸するような揺れ)
→ MiniはAttackをSlowへ。DeluxeならCleanを10〜20%混ぜる。
よくある質問(FAQ)
Q1:ベースでも使える?
→ 使える。DeluxeモデルのCleanブレンドを使えば低域を保ったまま圧縮できる。
Q2:真空管アンプとの相性は?
→ 非常に良好。入力段で整音が働く。
ただし強い入力信号ではSensitivityを下げめに設定するのがコツ。
Q3:ライブで毎回同じ音を出すには?
→ 時計表記でノブ位置を記録。写真メモ+固定電源で安定。
まとめ:Dyna Compは“足りないくらい”がちょうどいい
MXR Dyna Compは、ノブ2つで音の印象を劇的に変えるエフェクターだ。Sensitivityを上げすぎると不自然になるが、少し控えめに設定すると音が立体的に聴こえる。OutputとSensitivityを対で動かし、「効かせすぎない」バランスを探すことがポイント。
この記事の設定例をベースに、まずは自分のギターとアンプで回してみてほしい。Dyna Compの本質は、派手な“つぶし”ではなく、弾きやすさと抜けを同時に得ることにある。ほんの1ミリの調整で、あなたのトーンがプロ仕様となるはずだ。